豆の根っこと根粒菌
豆の水栽培
皆さんは、豆の根っこを見たことがありますか?

私は・・・ 枝豆の根っこの力強さに圧倒されたことや、落花生の根っこに殻付きピーナッツが着いているのを歓喜したことがあります。

そして、昨年から何回か「おうちでベジ」というキットを使って、豆の水栽培をしました。育てたのは、えんどう豆とレンズ豆。
こんな感じです。


左はえんどう豆、右がレンズ豆。
毎回、先に芽が出て、同時期にしょぼい根っこが出てきて、その後ぐんぐん茎も根っこも育っていきます。
えんどう豆は何回か収穫しているうちに、チュルチュルがもつれて手がつけられなくなり、最後のほうは無理やり引っ張って収穫する感じ。
可食部分を切り取ったあとに、容器の下部分に残った根っこを処理しながら思うのです。立派な根っこやなぁ、と。

水栽培するときは、出張で留守する日を除いて毎日、水替えをします。そのせいだと思うのですが、白く伸びた根っこがキレイ。容器の中に狭苦しそうに納まって、成長していきます。

水の中に育つ根っこに、根粒菌(こんりゅうきん)は見られません。豆粒は地上と水中に栄養を送って空洞になっていきます。
そもそも「根粒菌」とは
豆がらみでSDGs、サステナブル、FAOや国連の話が出てくるとき、よく登場するのが「根粒菌」です。根粒菌は豆の根っこに着く丸い粒ツブ。
話としては何度も耳にして、文字でも何度も目にしておきながら、「これが根粒菌ですよ」と初めて現物を見せていただいたのは、山形県鶴岡市でのことでした。

昨夏、取材で訪れた十五代 治五左衛門さんの畑でのこと。

「立派な根っこ!」と思ったものの・・・ 兼業農家の娘に育った私は、名前を知らなかっただけで、幼少期より何回もこの粒ツブを見ていたように思いました。見覚えがあると思いました。
豆の根っこによく着くと言われる根粒菌、イネの根っこにも着くよね? 麦の根っこにも着きますよね? 大根や白菜やジャガイモには?
根粒菌は豆だけに着くわけではなくて、豆の根っこに多く着く菌?
お百姓の娘に生まれておきながら、農業から逃げ腰で大人になったから、貴重な体験が何一つ身についていないのです・・・
根粒菌の働き
改めまして、根粒菌。

わかりにくいかもしれませんが、枝豆の根っこに着いている丸い粒ツブが根粒菌です。引っこ抜いたとき、土の中に残る根っこにいっぱい残っていると聞きます。
この根粒菌が良い土を作るのに役立ちます。植物が育つとき必要な栄養として窒素(ちっそ)があげられます。
土の中に存在する量で足りないと植物はすくすく元気に育たないため、農作物栽培には手軽に養分を与えるために窒素系肥料が撒かれます。
しかし、この化学肥料は土の中に残って環境汚染を招くことが後になって知られるようになりました。農薬や化学肥料は、本来、土がもっている力を弱め、疲弊した土になる・・・ というような話をかつて取材した農家さんたちから教わりました。
豆の根っこに着く根粒菌は、大気中に存在する窒素を土の中に取り込み、栄養成分として根っこから吸収できるように変えて、植物の成長〜実りを助ける働きをします。

豆を含む農作物の畑は、輪作を嫌います。必要とする栄養を土の中から吸収するため、豆(その他の植物)が喜ぶ栄養成分が減っているからです。「土を良くする」「力のある土を作る」と言われる豆を育てた畑は、次に育てる植物にとって、栄養のある土が集まった畑になります。
だから、豆殻や根っこは、ゴミにするのではなく一度乾かしてから、土にすき込む作業をされています。そうすると窒素系の化学肥料散布が減らせます。
これが、豆の栽培とSDGs、サステナブル(持続可能)な農業などに、豆が引き合いに出される理由のひとつです。
私は泥まみれ、埃まみれになって土と向き合う現場を、幼少期とここ15年くらい見てきました。農業の大変さを少しだけ知っています。だから、豆が農業の役に立つとしたら、応援したいと思うのです。がんばれ、豆! よろしくね。
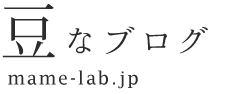







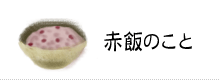
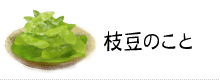
 豆・豆料理探検家
豆・豆料理探検家
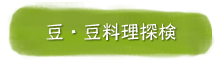

この記事へのコメントはありません。