10月11日 豆シンポジウム/東京
国際マメ年・豆の日 特別記念シンポジウム 2016
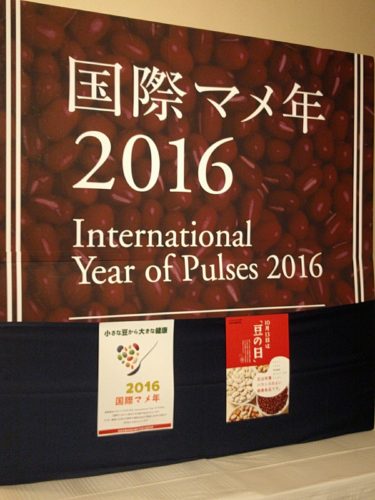

10月11日(火)11:00より、新宿の京王プラザホテルで豆のシンポジウムが開催されました。全国豆類振興会、日本豆類協会の主催で、農林水産省が後援のシンポジウムでした。

主催挨拶のあと、FAO(国際連合食糧農業機関)のボリコ所長が流暢な日本語で挨拶されました。
国連が毎年定められる国際年の中で「国際マメ年」については問合せ等が多く、日本での関心の高さを感じる、というようなお話もありました。
ボリコ所長は週に2回ほど、自国(コンゴ共和国)の豆をトマトソースで煮た料理を作り、子供たちに喜ばれていることや、自分では納豆や豆腐を毎日食べていることなど、親しみあるお話で結ばれました。
パネルディスカッションより
そして、藪光生 先生がコーディネーターを務められるパネルディスカッションへ。パネリストは北海道の加藤淳博士と、オレンジページの杉森一広 編集主幹、料理通信の君島佐和子編集長。読者層の異なる2つの食の媒体と、小豆のスペシャリストのお話は興味津々です。

オレンジページの「豆」に関するアンケート資料では、読者の8割近くが豆に関心を持っていて、健康に良い、おいしい、栄養豊富、美容に良いなどの理由で豆を食べているのだそう。
よく食べる豆料理は、ダントツで83.6%の人が「和食」と回答されていました。その半分以下の数値でサラダ、和菓子、スープ、カレーと続きます。人気の豆は、大豆、小豆、黒豆、ひよこ豆‥‥ とありました。
杉森氏のお話の中で「豆はどうやって食べたらいいか、わからない」「1粒1粒つまんで食べるのが面倒」などの声が多いというのも興味深かったです。「豆は天然のサプリメント、すごいな、豆」は、そのまま雑誌の見出しに使えそうな名セリフだと思いました。
君島編集長の資料は、見ているだけで自分でも作ってみたくなりました。フランスやイタリアで修業したシェフたちは、豆料理に愛着を持っているとのこと。フランスとイタリア、どちらももう一度行ってみたい。もちろん、豆料理の探検に‥‥。
フランスやイタリアの豆の煮方は、豆がおどらないように弱火で2〜3時間くらいかけて、香味野菜と共にゆっくり煮るそうで、そこも自分が覚えた料理手順と違うなと思いました。
キャビアに見立てたレンズ豆の料理の話も興味深くお聞きしました。「謙虚な食材に、どう光を当てていくか? 豆もその謙虚な食材のひとつ」なのですよね。
加藤博士のお話は、藪先生と響き合うものを感じました。「小豆を3日間食べ続けてください。便秘快復、デトックス効果が期待でき、美容と健康に良い」という話が記憶に残っています。
専門的なお話をたくさんお聞きできました。「僕はタネをまいて豆を栽培するところから、豆の料理を作っています」は、まるで私の実家の母が言いそうな言葉だなと‥‥笑
「小豆の甘くしない食べ方として、ミネストローネはスープの味がひき立ち、おすすめです」は、近々実践してみます。
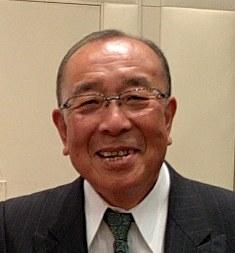 藪光生 先生は、豆についての様々なお話より「糖質ダイエットのような偏ったことをせず、どの食材もまんべんなく食べること」が響いてきました。お赤飯、黒豆ごはん、ヒヨコ豆の玄米ごはんなど、豆とごはんを上手に組合わせたら、白ごはんより糖質意識がやわらぐかも。
藪光生 先生は、豆についての様々なお話より「糖質ダイエットのような偏ったことをせず、どの食材もまんべんなく食べること」が響いてきました。お赤飯、黒豆ごはん、ヒヨコ豆の玄米ごはんなど、豆とごはんを上手に組合わせたら、白ごはんより糖質意識がやわらぐかも。
一般のご家庭の食卓に、ニコニコした表情の豆まじりのゴハンも並ぶといいなと思います。
「豆にはカリウム、カルシウム、亜鉛などのミネラルが豊富」についての具体的な話のすき間に、「まるで鉄鋼屋のオヤジみたいですが‥‥」と。さすが、藪先生ならではのお言葉です。笑
世界の豆料理を食べよう
京王プラザホテルのシェフが作られた全14品の豆料理が、ホテルの広々とした開場に並びました。まるで立食パーティのよう。300名の立食は圧巻です。参加者の平均年齢は60歳前後? 男性も多数おられます。


Yさまといっしょに味わうことができた料理は、
・レンズ豆のサラダ (レンズ豆)
・ミネストローネスープ (白いんげん豆)
・レンズ豆のポタージュスープ (レンズ豆)
・ポークビーンズ (白いんげん豆)
・眉豆と黒豆、スペアリブの煮込み (眉豆=ハタササゲ、黒豆)
・大豆と落花生、鶏肉のサイの目切り 山椒辛子炒め (大豆、落花生)
・あずきと緑豆入りもち米ごはん (あずき、緑豆)
・大豆と桜えびのつまみ揚げ (大豆)
・呉汁 (大豆)


(途中で舞い上がるような嬉しい出来事があり、料理写真は少しだけしか撮れていません)
ホテルの料理は、もちろん絶品でした。ひとつ、呉汁の素朴さだけは家庭料理のような味わいで親しみをおぼえました。レンズ豆のポタージュは、レンズ豆の味がしっかり感じられて、いいなと思いました。
無料で参加させていただいたシンポジウムで、このように手のこんだ豆料理の数々を味わうことができるとは! 主催団体さん、協力会社さんの「国際マメ年」「豆の日」にかける意気込みを実感し、この場に参加させていただけたことを有り難く思いました。
そして、豪華おみやげも‥‥(^^) 明日につづく
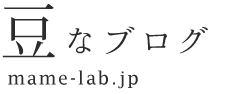







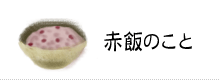
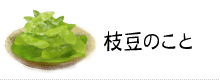
 豆・豆料理探検家
豆・豆料理探検家
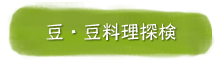

この記事へのコメントはありません。