仙太郎の「花びら餅」と足利義詮公
花びら餅の始まりは〜京都・吉田神社に残る鈴鹿家の日記
先日のリカレント講座でお聴きした奥村彪生(あやお)先生のお話に触発され、このお正月に食べ損ねていた「花びら餅」を買ってきました。京都伊勢丹の仙太郎さんの花びら餅です。

これまで、お正月にいただく御菓子として年毎に、どこかの和菓子屋さんが作られたものを買い求めてきましたが、その始まりをお聞きしてみると、なるほどと納得します。
「ひし花びら餅」として吉田神社に残る鈴鹿家の日記に、二代将軍 足利義詮(よしあきら)公に献上した記録があるそうです。その「ひし花びら餅」を再現したお写真も見せていただきました。
義詮公は、室町幕府をひらいた将軍・足利尊氏公の嫡男で、1330年生まれで1367年に亡くなられています。没年はおよそ650年前ですから、花びら餅の原型は650年以上前には既に存在していたということになります。
ひし花びら餅は、真四角の形を菱形になるようにおいて、その中に餡や牛蒡などを入れておられました。雑煮は京都発祥とのこと、だから花びら餅も白味噌味の餡が入っているのですね。
初春を祝う餅菓子
そんなことを思い浮かべながら、仙太郎さんの花びら餅を味わいました。別名「葩餅(はなびらもち)」「菱葩(ひしはなびら)」「お葩(はなびら)」とも表わすとのこと。
仙太郎さんの花びら餅に、梅の花をかたどった干菓子が添えられているのは、単なる箸休めの役割ではなく、牛蒡と共に長寿を願う「歯がため」の意味があるのでしょうね。
京のお正月雑煮を和菓子に見立てた花びら餅、本当は大福茶(大服茶)でいただくのだそう。元旦に若水を沸かした湯に、梅干、結び昆布等を入れて飲むお茶が「大福茶」、一年の邪気を払う意味があるそうです。

(写真は八女茶です)
あぁ、正月も六日、七日になって知ること、思い出すことだらけ。今年の年末にこの記述を読んで、大福茶や花びら餅の用意は大晦日までに済ませなくてはと思いました。忘れないように、2018年12月のところに書いておかねば‥‥
そして、せっかくだったら一度くらい、八坂さんに「おけら火」をいただきに行きたいです。バス、電車は火が残る縄を持っていたら乗車できませんから、タクシー(乗せてくれるでしょうか?)か自転車か、歩きで帰ることになる?? う〜ん。それもまた、大晦日の珍事で良いかもしれません。
元旦におけら火で沸かした湯を用いて大福茶を入れ、花びら餅を味わう。それは、聖なるお正月の雑煮を祝ってからですね。あぁ、次のお正月が楽しみです(^^)
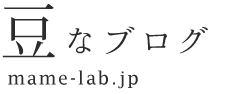







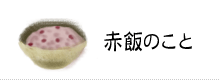
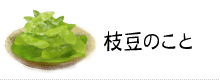
 豆・豆料理探検家
豆・豆料理探検家
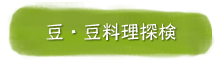

この記事へのコメントはありません。