手習い「しもつかれ」風
栃木県の郷土料理「しもつかれ」
節分前に「しもつかれ」という料理を、関東と京都の2拠点で生活する友人に教わりました。
しもつかれは初午の頃に、赤飯と一緒に稲荷神社にお供えする料理だそうです。
鮭・節分豆・大根・ニンジンなどの根菜・お揚げ・酒粕が入っていると、口頭で材料を聞いて、想像で勝手に作ったら大ハズレ。
それからネット検索でレシピを見つけ、作ったものを友人に食べてもらうと、「前より近づいたけど、まだ違う」と、今度は本を貸してくれました。
大ハズレ以降、3回〜4回作ったら、自分の味が固まりました。
本場の「しもつかれ」を一度も食べたことがないから、「しもつかれ風」。
食べた人たちは、皆さん「しもつかれ? 知らない」「食べたことない」と。
ごめんなさいね。そんな人たちに食べさせて。男性も女性も、延べ7〜8人が私の作った「しもつかれ風」を「しもつかれ」の味と思ったかもしれません💦
地元では「しもつかれコンテスト」まで開催されているようです。そんな郷土愛に守られている料理を、モグリの京都市民が見よう聞きかじりで作ったりして・・・
しもつかれ風 おぼえ書き
私は、酒のアテにしても合う自分の味が好きだから、このまま「しもつかれ風」を貫きます。
次回つくるときのための、おぼえ書き。

▲ こちらは4回目の作
[材 料]
・節分の煎り豆、もしくは煎り大豆 約30gほど
・鮭の切り身 1切
・大根 10cmほど
・人参 1/2本
・油揚げ 10cmほど
・酒粕 10cm×10cmほど
・昆布 5cmほど
・酢 小さじ1
・塩 小さじ1/2〜1
・醤油 小さじ1〜2
・仕上げに粉末の柚こしょう
[作り方]
① 昆布は、ぬるま湯に浸して出汁を引く
② 別鍋に湯を沸かし、酢を加えて鮭の切り身を湯通しする。熱が通ったら湯切りして、身をほぐす
③ 油揚げはオーブントースターで両面を3分ずつ加熱し、5㎜角に切る
④ 鬼おろしを使って、大根と人参を粗くおろす
⑤ ①から昆布を取り出し、鍋に移す。④の大根・人参(おろし汁とも)、節分豆(または、煎り大豆)、③の刻んだ揚げ、②の鮭ほぐし身を加え、蓋をして弱火で加熱。
⑥ 20分〜30分ほど煮ている間に酒粕を刻み、熱湯でゆるめる。⑤に加え、軽く混ぜて更に5分〜10分加熱する。
⑦ 塩、醤油で味を調え出来上がり。常温に冷まし、味を含んだら食べごろ。好みで柚コショウをかける。

▲ こちら2回目の作。これが最も私好み
先述の友人曰く「しもつかれはもっと汁気が多い。酒粕が強すぎる」と。
そうなのですね。あぁ、一度、本物を食べてみたいです。
初午の頃の栃木県を訪ね、お総菜売場をリサーチしてみたら売ってるでしょうか?
しもつかれ〜〜〜


▲ 3回目と5回目のしもつかれ
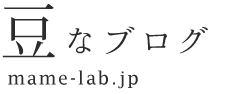







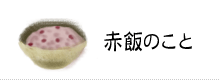
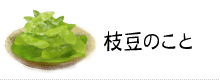
 豆・豆料理探検家
豆・豆料理探検家
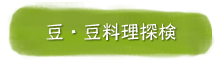

この記事へのコメントはありません。